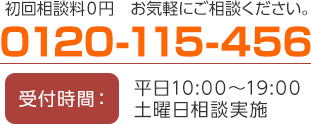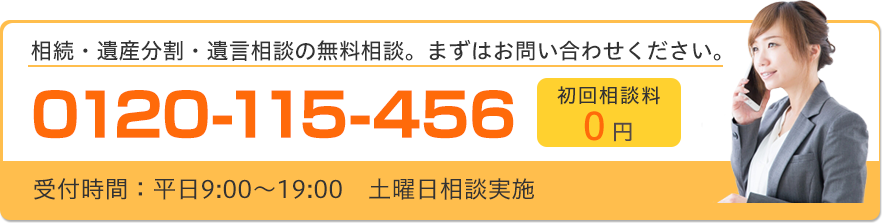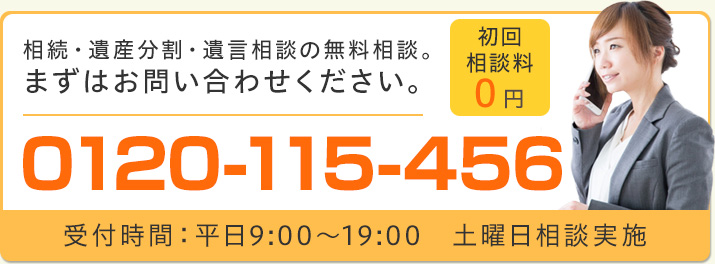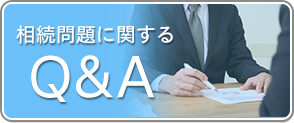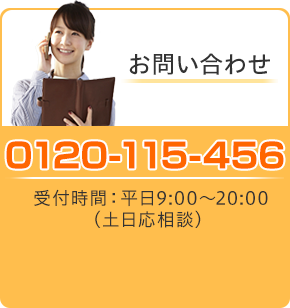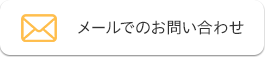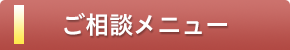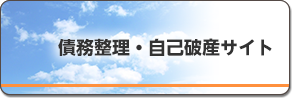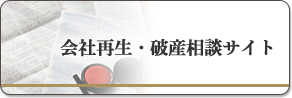第18.遺留分を裁判所で争う訴訟のポイント
遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)訴訟を提起する必要があります。遺留分額の計算方法、遺留分侵害額を請求するための協議、調停、裁判手続の流れ、費用や注意点について解説します。
第18.遺留分を裁判所で争う訴訟のポイント
遺留分が侵害されている場合は、1年以内に遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行わなければなりません。遺留分が侵害されていることに気づいたら速やかに内容証明郵便を送付し、協議の成立が見込めない場合は、裁判手続を踏まなければなりません。
遺留分を裁判所で争う方法としては、調停と訴訟があります。
当事者間の協議から調停、訴訟までの流れと注意点について解説します。
遺留分とは
遺言書で遺産を取得できないことになった相続人は、遺言書により遺産を多く取得した受遺者、相続人から、一定限度の遺産を取り返す制度です。
また、遺言書が無くても、遺産のほとんどが生前贈与され、遺産からの相続財産が少なくなった相続人は、多く取得した受遺者から一定限度の遺産を取り返すことができます。
遺言書や生前贈与によって遺留分に達しない遺産しか相続できない状態を「遺留分が侵害されている」と表現します。
遺留分の計算方法
計算の概要
まず、いくら取り返すことができるのかを検討するにあたり、遺産から自分に最低限確保されるべき金額(遺留分額)がいくらあるのか計算する必要があります。
遺留分額が決まれば、現実に受け取った遺産との不足分(遺留分侵害額)を確定し、これを相続人や受遺者に返還していくことになります。
遺留分額の計算
現に残っている遺産だけを基準とすると、生前贈与により遺留分すら満足できない額しか残らない場合がありえます。そのため、遺留分額を計算するときは、生前贈与された額を加算して債務を控除した金額を対象に個別的遺留分率を乗じます。
個別的遺留分率は、それぞれの法定相続分に総体的遺留分を乗じたものです。
総体的遺留分は、2分の1もしくは3分の1です。
遺留分額の算出方法
(被相続人が相続開始時において有した財産の価額 + 生前に贈与した財産の価額 - 債務)× 個別的遺留分率 = 遺留分額
遺留分侵害額
遺留分額がわかれば、次に、遺留分侵害額を計算することになります。
自己が現に受け取った財産が、遺留分額に達しているのか確認し、遺留分額に達していない場合には、不足する金額(遺留分侵害額)を取り返すことができます。
なお、遺留分額を計算するにおいて、生前贈与の額を加算したこととの均衡上、遺留分侵害額の計算において、過去に自己が生前贈与によって受けた分を差し引いて計算する必要があります。
遺留分侵害額の計算
遺留分額 -(自分の相続による取得額 - 相続債務分担額)-(自分が取得した特別受益の受贈額 + 自分が取得した遺贈額)= 遺留分侵害額
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の期限
遺留分を主張して、遺留分額に不足する金額の返還を求めることを遺留分侵害額請求と言います。かつては、遺留分減殺請求と呼ばれていました。
遺留分侵害額請求は、死亡の事実及び遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知った時から1年で時効により消滅します。
また、死亡日から10年を経過すれば、遺言書の存在を知らなくても請求できなくなります。(民法1048条)。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
遺留分減殺請求の制度は、2019年7月1日から、遺留分侵害額請求に変わりました。
遺留分の概念や遺留分を請求できる点に大きな違いはありません。
変わった点は、遺留分減殺請求が現物返還を求める請求権であるのに対して、遺留分侵害額請求は金銭の支払いを求める請求権である点です。
遺留分減殺請求では、不動産が遺言によって遺贈されたり、生前に贈与された場合は、その不動産の返還を求めるのが原則でした。
遺留分侵害額請求では、不動産が遺贈や贈与された場合でも、その不動産の返還は請求できず、その不動産の価額に相当する金銭の支払いを請求できるのにとどまります。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求権を行使する方法は、協議、調停、訴訟の3つです。
いずれの手段を講じるにしても、遺留分侵害額請求を行使する旨の意思表示を行っておく必要があります。
内容証明郵便を送付する
遺留分侵害額請求権が時効で消滅しないように、1年以内に遺留分を請求する旨の意思表示を行う必要があります。
口頭でも遺留分を請求することはできますが、証拠が残るよう内容証明郵便で送付すべきでしょう。
このとき、遺留分侵害額請求権を行使する旨を明示しましょう。
内容証明郵便を送付することにより、遺留分侵害額請求権の消滅時効完成を6カ月間猶予することができます(民法150条1項)。
協議
遺留分を侵害されている相続人と遺留分を侵害している受遺者や相続人が話し合いにより解決する方法です。
内容証明郵便による請求に対して相手から返信を受けた場合は、その内容次第で協議を行うことができます。
ただ、協議が長引く場合は、遺留分侵害額請求権の消滅時効が成立してしまうため、早めに調停を申し立てる必要があります。
調停
遺留分に関して当事者同士の話し合いがまとまらない場合は、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
家庭裁判所の場所は、調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停は、非公開の場で行われ、当事者同士が対面しなくても、調停委員や代理人を通じて解決を図る制度です。
遺留分制度は法律上の制度ですので、受遺者はこれに従い返還するしかないため、ほとんどの事例において、調停か、調停前の話合いにより解決されます。
話し合いがまとまれば、調停調書が作成されて遺留分侵害額の清算が行われます。
遺産を巡る争いの調停方法としては、遺産分割調停もあります。
遺産分割調停は、一般的には遺言書がなく相続人同士で遺産の分け方について揉めている場合に申し立てる手続です。
遺産分割調停がまとまらない場合は、家庭裁判所の裁判官が自動的に審判手続を行い、一切の事情を考慮して審判を下す形になります。
つまり、調停が成立しない場合は審判という流れになります。
それに対して、遺留分侵害額の請求調停では、調停不成立となっても自動的に審判が開始されるわけではありません。
そのため、調停が成立しない場合は、地方裁判所への訴訟を提起する必要があります。
訴訟
調停で話合いが成立しない場合には、地方裁判所(請求額が140万円を超えない場合は簡易裁判所でもよい)に対して、民事訴訟を提起する必要があります。
訴状の提出先は、次の3つのいずれかです。
- 被告の普通裁判籍の所在地
- 原告の所在地
- 被相続人の相続開始時における普通裁判籍の所在地
遺留分侵害額請求訴訟では、主に、遺産の額、債務の額、生前の贈与の有無・額、遺産の評価額などが審理されます。
原告側(遺留分侵害額を請求する側)が遺留分侵害額につき、主張し、立証しなければなりません。
遺留分侵害額の計算は複雑になることが多く、弁護士の関与が事実上必要不可欠な訴訟類型となっています。
訴訟になった場合は解決まで時間がかかりますし、大変な労力を要するため、できれば、調停の段階から弁護士が関与して、訴訟に発展する前に解決することが望ましいです。
遺留分侵害額請求訴訟は、訴訟上の和解又は判決によって終了します。
訴訟上の和解は、訴訟の途中で裁判所が和解を提案する場合です。
裁判所が提案した和解案を原告と被告の双方が受け入れれば、和解調書が作成されて、訴訟が終了します。
当事者が和解を受け入れず、訴訟が進行した場合は、最終的に裁判所が、判決を言い渡します。
判決に対して不服がある場合は、判決書の送達から2週間以内に控訴をすることができます。
当事者のどちらも控訴しない場合は、判決が確定し、判決書に基づいて、遺留分侵害額の清算が行われます。
遺留分侵害額請求訴訟を提起すると解決まで1年かかる
遺留分侵害額請求訴訟を提起した場合、解決まで、約1年かかってしまうのが一般的です。
原告が遺留分を侵害されているとの主張を行うと、被告は遺留分の基礎となる財産の額が異なるといった主張を行うことがあります。
また、相続財産に不動産がある場合は、評価額を巡る争いが生じることもあります。
裁判所は判決を下すに当たっては、双方の主張をよく聞かなければなりませんし、争点を明らかにする必要があることから、慎重に審理を進めていきます。
そのため、判決を出すまで、約1年近い期間がかかってしまいます。
約1年もかかると、遺留分侵害額請求権の消滅時効が過ぎてしまうのではないかと懸念される方もいらっしゃるかもしれませんが、その点は心配ありません。
遺留分侵害額請求権の消滅時効が到来する前に訴訟を提起していれば、訴訟を行っている間は、消滅時効が進行しないことになっています。これを時効の完成猶予と言います。
そのため、被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分侵害額請求訴訟を提起していれば、ほとんどの場合、問題ありません。
遺留分侵害額請求の裁判手続きにかかる費用
裁判手続を使って遺留分侵害額請求を行う場合は、裁判所に納める手数料等が掛かります。
具体的に確認しましょう。
調停の費用
遺留分侵害額請求調停を申し立てる際は裁判所に収める費用(実費)が掛かります。
具体的には次の2点です。
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
訴訟の場合と比べると費用は少なくて済みます。
訴訟の費用
遺留分侵害額請求訴訟を提起する場合は、裁判所に収める費用(実費)と弁護士に依頼するための費用がかかります。
裁判所に収める費用(実費)の内訳は次のとおりです
- 手数料
- 郵便切手代
手数料は、遺留分侵害額請求で請求する額により異なります。
多額であれば、手数料も高くなります。
郵便切手代は、裁判所から原告・被告に対して郵便物を送るためにかかる費用のことです。
弁護士に依頼するための費用
弁護士に依頼するための費用は、弁護士事務所により異なります。
初期費用として相談料や着手金をお支払いいただき、遺留分侵害額を回収できた場合に成功報酬を頂く形が多いです。
遺留分侵害額請求の必要書類
遺留分侵害額請求について裁判手続を利用するためには様々な書類が必要になります。
訴訟を提起するために弁護士に依頼した場合は、弁護士が大半の書類を用意しますし、当事者が準備すべきものは案内します。
一方、調停では自分で手続きをする方もいらっしゃるかと思いますので必要な書類を紹介します。
- 申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の写し
- 内容証明郵便の控え
- 遺産に関する証明書
申立書は家庭裁判所に記載例が用意されているので参考にして作成します。また、遺産目録も併せて作成します。
戸籍謄本は、死亡している方については、出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍が必要になります。
遺言書は、検認が必要なものについては、検認調書謄本の写しを用意します。
遺産に関する証明書としては次のようなものを用意します。
- 不動産に関する証明書:不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 預貯金に関する証明書:預貯金通帳の写しまたは残高証明書
- 有価証券に関する証明書:残高証明書
- 債務に関する証明書:ローン残高証明書
遺留分問題は早めに弁護士へご相談ください
遺留分が侵害されている場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。
遺留分侵害額の請求権は、被相続人が亡くなった日又は、遺留分を侵害する贈与または遺贈があった日から1年間で時効によって消滅してしまいます。
内容証明郵便を送っただけでは、その期間を6ヶ月猶予できるに過ぎません。
相手方は協議を先延ばしにして、遺留分侵害額請求権の消滅時効が成立するのを狙っている可能性もあります。
相手方が話し合いに応じる気がない場合は、迅速に調停や訴訟を提起する必要があります。
そのためには、できる限り早めに弁護士に相談して対策を練るべきなのです。
- 第1.死亡後に必要な届けや手続きの一覧と届出先・必要なもの
- 第10.相続に必要な出生から死亡までの戸籍謄本等の取り寄せ方
- 第11.遺産分割の全体像(遺産分割協議書の作成・法定相続分・具体的相続分・寄与分・特別受益・分割方法)
- 第12.死亡直後に問題となる故人の契約(賃貸契約・水道光熱費・クレジットカード)の相続手続・清算方法
- 第13.相続の放棄のメリット・デメリットと相続の放棄の期間・手続
- 第14.死亡した家族の所得税・相続税の申告・納税の手続
- 第15.家族が業務中に死亡した場合の労災保険の申請や損害賠償の流れ
- 第16.遺産分割協議書には何を書けばいいのか
- 第17.遺言書による名義変更・相続手続の流れ
- 第18.遺留分を裁判所で争う訴訟のポイント
- 第19.遺産分割の調停と遺産分割の前提問題に関する訴訟のポイント
- 第2.遺族が忘れずに申請しておくべき葬祭費・埋葬料・遺族年金などの手続
- 第20.遺産分割事件の長期化によるリスク
- 第21.相続時に親子関係や認知を裁判で争うポイント
- 第22.使途不明金を争う訴訟のポイント
- 第3.葬儀費用と香典で遺産相続トラブルを避けるための記録・清算のポイント
- 第4.お墓の管理と相続でトラブルにならないための2つのポイント
- 第5.葬儀費用を争う訴訟のポイント
- 第6.故人の免許証の返還手続
- 第7.遺産(不動産、保険、株式、投資信託など)の名義変更・相続手続
- 第8.遺言書の発見と確認方法
- 第9.相続人の範囲と優先順位・相続分の割合について解説