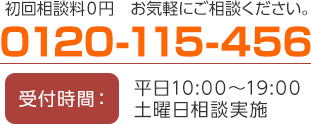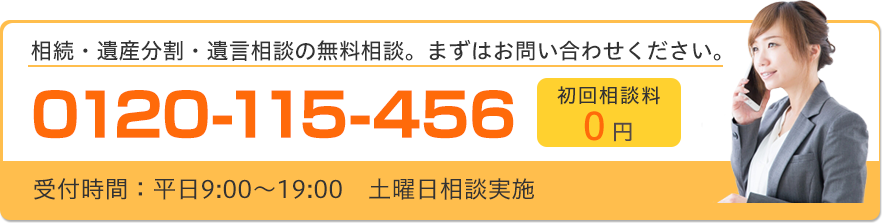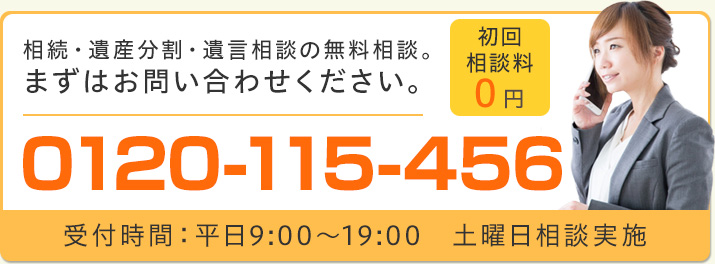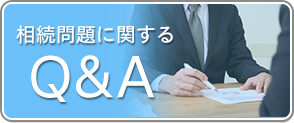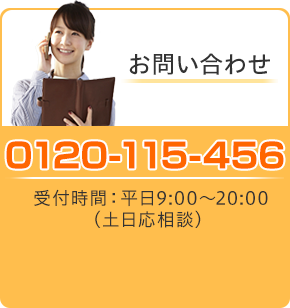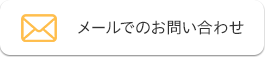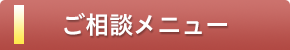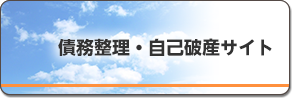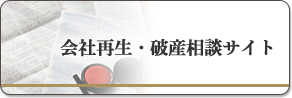遺産分割協議に成年後見人が参加するときの基礎知識と注意点とは?
認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が著しく低下すると、騙されたり不利益を被ったりする恐れがあるため、サポート体制を整えておくことは非常に重要です。
そういう意味で、成年後見制度は社会的に非常に大切な役割を持つ制度といえるでしょう。
成年後見制度があることで、本人や家族は安心して生活していくことができるのです。また、成年後見制度は相続においても大きな役割を果たします。
今回は、遺産分割協議に成年後見人が参加するときの基礎知識と注意点を解説します。本記事を読むと、成年後見人が遺産分割協議に参加するときに知っておきたい基礎知識と注意点だけでなく、成年後見人選任までの流れが分かるので、相続時のトラブルを防ぎたい方や、判断能力が著しく低下している人が相続人にいる方は、ぜひご一読ください。
成年後見人に関する基礎知識
成年後見人という言葉を聞いたことがあるけれど、正確な意味を把握していない方は少なくありません。そこで、まずは成年後見人に関する基礎知識から見ていきましょう。
成年後見人とは
認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が著しく低下した人は正しい判断ができないことがあります。そのため、周りのアドバイスを受けずに契約などを結ぶと、騙されたり不利益を受けたりする危険性があるのです。
このような状況を防ぐために、判断能力が著しく低下した人の法律行為は基本的に無効とみなされることになっています。しかし、これでは判断能力が著しく低下した人は、契約の締結や法的な手続きを行うことができません。そこで、本人に代わり契約の締結や解除、財産の管理を行う成年後見人を立てることができるようになっているのです。
成年後見人を立てることで、判断能力が著しく低下した人の権利や財産を保護することができます。
成年後見人の役割
成年後見人の役割は、成年被後見人の代わりに本人の権利や財産を守ることにあります。主な役割は下記の3つに分かれます。
財産管理
身上監護
監督と報告
ここからは、それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。
財産管理
財産管理とは、成年被後見人の不動産や財産を管理して守ることを指します。判断能力が著しく低下した状態では、騙されて高額な商品を購入させられたり、本人にとって不利益になるような不動産売買が行われたりすることがあります。これらの事態が起こらないように、成年後見人が財産を管理して守っていくのです。
成年後見人は、財産目録と年間収支予定表を作成・提出したうえで、年金などの収入を管理しながら計画に基づいた支出を行っていきます。
また、相続が発生した場合には公平な相続実現のために、遺産分割協議に参加することも財産管理に含まれます。
身上監護<
判断能力が著しく低下した状態では、必要な福祉サービスや医療を受けることが難しくなります。そのため、身上監護も成年後見人が果たす大きな役割です。
具体的には、介護サービスや施設入所などに関する契約の締結や解除、医療に関する契約の締結や解除が該当します。この時、大切になるのが本人の意思を最大限尊重することです。
成年後見人の最も大切な役割は、本人を守ることにあるので、本人の意思を最大限尊重することが求められます。
ここで押さえておきたいポイントが、食事のお世話や実際の介護作業は成年後見人の職務に含まれないことです。ここでいう身上監護は、あくまでも安心して生活できる環境を整えるためのものであり、食事や介護作業といった直接的なものは介護サービス事業者が担当することになります。
監督と報告
成年後見人は定期的に家庭裁判所に職務の進捗状況を報告しなければいけません。これも、成年後見人が果たす大きな役割の1つです。
この時、必要になるのが後見等事務報告書や財産目録、本人収支表などの書類です。定期的に報告することで、より安心できる環境を構築することが目的とされています。
遺産分割協議と成年後見人
成年後見人の役割の1つが財産管理です。そして、相続における遺産分割協議への参加も基本的に財産管理に該当します。ここで基本的にと記した理由は、遺言書がある場合は遺産分割協議への参加が必要ないケースもあるからです。
遺言書が残されている場合は、基本的に遺言書に記載されている内容に従って遺産は分割されます。そのため、遺産分割協議は必要ありません。ただし、遺言書の内容が特定の相続人に遺産のすべてを相続するという内容だった場合は話が変わります。なぜなら、遺言書にいかなる内容が記載されていたとしても、遺留分(法廷相続人に対して最低限保障されている遺産の割合)が存在するからです。このような場合は、遺留分を請求することができるので、必ずしも遺言書の内容がすべてだと勘違いしないようにしてください。
また、不動産など分割が難しい遺産がある場合は取り扱いに注意が必要です。遺産に不動産が含まれている場合は、相続人全員の合意がなければ不動産の売却も解体もできません。このような場合、判断能力が著しく低下している人は同意ができないので管理処分が難しくなります。そのため、遺産に不動産などが含まれている場合は、早めに成年後見人を立てて対策しておく必要があることを覚えておきましょう。
一方で、遺言書が残されていない場合は、相続人全員が参加して分配方法を決める「遺産分割協議」の実施が必要です。遺産分割協議は法律行為に該当するため、判断能力が著しく低下した人が参加した場合は無効扱いになります。そのため、相続人の中に判断能力が著しく低下した状態の人がいる場合は、成年後見人が本人に代わり遺産分割協議に参加しなければいけません。成年後見人は本人に代わり参加するので、本人の不利にならないように他の相続人と協議していきます。
遺産分割協議が成立しないまま放置すると、遺産は相続人全員の共有状態のままとなるので、不動産の名義変更はもちろん、預貯金の解約を行うこともできません。そのため、トラブルを防ぐためにも早期に実施することが重要です。
遺産分割協議で成年後見人ができること
相続人に成年被後見人が存在する場合は、本人の代わりに成年後見人が参加して遺産分割協議を実施しなければいけないことが分かりました。では、成年後見人は遺産分割協議で何ができるのでしょうか?ここからは、遺産分割協議で成年後見人ができることを詳しく見ていきましょう。
遺産分割協議への参加
成年後見人が遺産分割協議に参加する目的は、本人の財産を管理して守ることにあります。ただし、成年後見人がすべてを判断できるわけではありません。なぜなら、成年後見人は家庭裁判所と相談したうえで協議に参加するからです。家庭裁判所は本人の利益を守る観点から協議内容に問題がないのかを判断します。そのため、最低でも法定相続分に相当する遺産が受け取れないような内容であれば合意は基本的に難しくなるでしょう。
遺産分割協議に成年後見人が参加する場合は、このような背景があることも理解しておく必要があります。
相続放棄と限定承認
成年後見人は、本人に代わり相続放棄や限定承認を行なえます。この申し立てには家庭裁判所の許可は必要ありません。ただし、実際は家庭裁判所と相談しながら進めていく必要があるので、独断で判断することは難しいのが現実です。
基本的に、相続放棄が認められるのはプラスの財産よりもマイナスの財産が多い状態になります。マイナスの財産が多い状態で相続すると負債を背負うことになるので、本人が不利益を受けることになります。このような状態を避けるために選択されるのが基本です。
ただし、相続放棄を選択するとプラスの財産も相続できなくなるので、慎重に判断しなければいけません。
相続登記・相続税申告
不動産を相続すると名義変更を行わなければいけません。なぜなら、名義変更ができていないと、不動産の所有を主張することができないからです。これらの相続登記も成年後見人が本人の代わりに行うことができます。ただし、必ずしも成年後見人が行わなければいけないというわけではありません。なぜなら、本人に代わって弁護士などの専門家に手続きを委任することができるからです。なお、専門家に依頼した際の費用については成年被後見人の財産から支払われることになります。
また、相続により発生する相続税についても同様の扱いとなり、税理士に手続きを依頼することが可能です。
遺産分割において成年後見人を申し立てるときの注意点
遺産分割において成年後見人を申し立てるときは、以下の点に注意しなければいけません。
早めの対応
利益相反関係
専門家への依頼
特に「早めの対応」は重要です。滞りなく相続を終わらせるうえでも、無用のトラブルを防ぐうえでも早めの対応は重要になるので、相続が発生しそうになった段階で早めの対応を心がけてください。
早めの対応
成年後見人選任の申し立ては、審判確定までに2~3か月程度の期間がかかります。準備などを含めると、もう少し余裕を持たせておくことも重要です。
相続手続きの中でも、相続税申告は「10か月以内」という期限が定められているので、早めの準備が大切になります。直前になって慌てることがないように、余裕を持ったスケジュール作成を意識しましょう。
利益相反関係
利益相反関係にある場合は、成年後見人になることができません。利益相反関係とは、特定の行為が、一方の利益になると同時に、もう一方の不利益に繋がる可能性がある関係性のことです。
遺産分割においては、親族といえども相続人同士の場合は利益相反関係にあたるので成年後見人になることができません。
ここで押さえておきたいポイントが、相続発生前から成年後見人になっていたケースです。例えば、相続発生前から長男の成年後見人に次男がなっていたケースなどが該当します。このような事例では、相続が発生する前から成年後見人になっていたので、遺産分割協議においても引き続き成年後見人としての役割を果たしていくと考えるかもしれません。しかし、長男と次男は共に相続人になるので利益相反関係にあたり、成年後見人として遺産分割協議に参加することができません。このような場合は、特別代理人の選任を申し立てることになるのです。
利益相反関係に該当する場合は、特別代理人の選任が必要になることを覚えておきましょう。
専門家への依頼
遺産分割協議を含む相続手続きには、専門的な知識が求められる場面が少なくありません。そのため、成年後見人になるのを躊躇われる方もいらっしゃいます。ここで1つの選択肢になるのが専門家への依頼です。弁護士などの専門家に依頼することで、不安を残すことなく相続手続きを終わらせることができます。また、専門家が入ることでトラブルの防止にも繋がるので、少しでも不安が残る場合は早めに専門家への依頼を検討することをおすすめします。
費用面を心配される方もいらっしゃいますが、弁護士事務所の中には無料相談を実施しているところも少なくないので、気になる場合は無料相談を活用してみましょう。
成年後見人選任までの流れ
成年後見人の申し立ては裁判所様式の書類セットの入手から始まります。これらの書類は裁判所のHPからダウンロードできるので裁判所に行く時間が確保できない方は、ダウンロードを活用してください。ただし、各家庭裁判所によって様式が多少異なるケースがあるので、ダウンロードする書類は必ず管轄の裁判所のHPからダウンロードしましょう。
書類をダウンロードしたら、書類の中にある「診断書」の作成を医師に依頼してください。なお、診断書の作成は認知症などの専門医でなくても問題ありません。また、診療科目の指定もないので「かかりつけ医」がいる場合は「かかりつけ医」に依頼して大丈夫です。
また、戸籍謄本や住民票(共に発行から3か月以内のもの)など公的書類も必要になるので、早めに準備しておきましょう。
他には、財産の内容や収支に関する書類、身上監護において必要となる書類を福祉関係者に作成してもらうことが必要です。さらに、後見人候補者の住民票または戸籍附票も必要になるので忘れないようにしてください。
以上の書類を揃えたら、管轄の家庭裁判所に申し立てます。ここでの注意点は、管轄の家庭裁判所は住所ではなく居所で決まることです。病院や施設に入所している場合は、管轄の家庭裁判所がどこになるのかを確認しておきましょう。
書類が提出されたら、面談や調査を重ねて家庭裁判所が審査を行います。なお、審判が確定するまでの期間はおおよそ2週間程度とされています。
以上が、成年後見人選任までの流れです。読んでいただくと分かる通り、意外に時間と労力がかかるので、仕事をしながら手続きを行うことは簡単ではありません。弁護士に依頼すると、これらの作業をすべて任せることができます。少しでも不安が残るようであれば、早めに弁護士への依頼を検討しましょう。
まとめ
相続人の中に判断能力が著しく低下した状態の人がいると、遺産分割協議を進めることができません。なぜなら、判断能力が著しく低下した状態の人が行った法律行為は無効になるからです。そのため、相続手続きを進めるには成年後見人の選任を行う必要があります。
ただし、利益相反関係にある場合は成年後見人になることができません。そのため、成年後見人の人選で悩まれるケースもあるでしょう。このような場合は、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼することで、スムーズに相続手続きを進められるだけでなく、トラブルを防ぐ効果もあるからです。
相続が長引くとトラブルに発展することも珍しくありません。このような状況を避けるうえでも弁護士や司法書士などの専門家への依頼は有効です。少しでも不安がある方は、まずは無料相談を利用してみましょう。