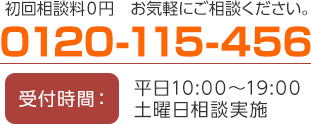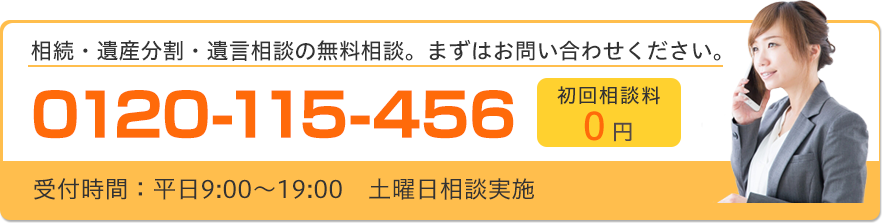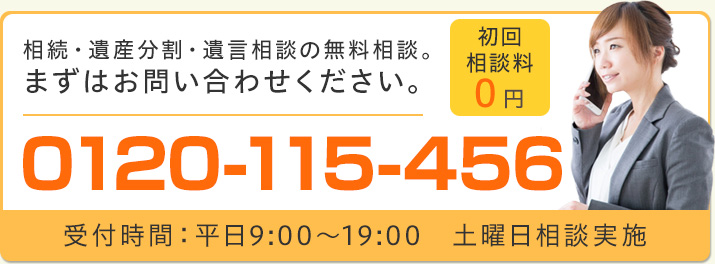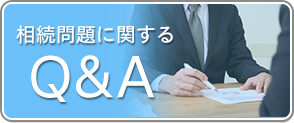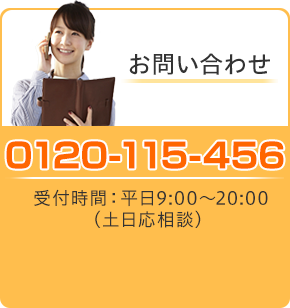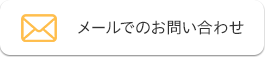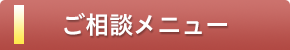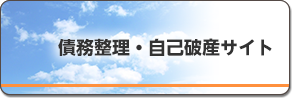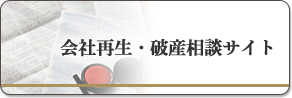話題の家族信託とは?相続時の注意点や制度のしくみを解説
高齢社会の日本において、柔軟な資産運用ができる「家族信託」は年々注目度が高まっています。しかし、成年後見制度と比較すると未だに認知度は低く、相続時にはどのような影響があるのか気になる方も多いでしょう。
家族信託についてインターネットで検索すると、「相続対策の効果はない」という情報も多く、実際の利用に不安を感じている方も少なくありません。そこで、本記事では話題の家族信託について相続時の注意点や制度のしくみを中心にわかりやすく解説します。
家族信託とは
家族信託とは、財産を所有する人(委託者)が、自分の財産の管理や運用、処分を信頼できる家族(受託者)に託す財産管理方法です。
高齢社会が進む近年、認知症などにより高齢となった家族の認知能力の低下により、財産が凍結され、生活費や介護費用が引き出せなくなるリスクが高くなっています。
家族信託は、こうした事態に備え、本人が元気なうちに家族と契約を締結し財産を柔軟に管理・活用できるようにする制度です。この章では家族信託のしくみや、注目されている理由をわかりやすく解説します。
家族信託のしくみ
家族信託のしくみには、主に以下の3つの役割が登場します。
①委託者: 財産を託す人です。財産の所有者本人を指します。
②受託者: 託された財産を管理・運用・処分する人です。通常、財産を託される家族(子など)がこれにあたります。
③受益者: 信託された財産から発生する利益を受け取る人です。家族信託では①の委託者自身が受益者となることが一般的です。
例えば親(委託者)が元気なうちから認知症に備えて、不動産や預貯金(信託財産)の管理を子(受託者)に任せ、生活費や介護費用として使うための利益を親自身(受益者)が受け取る」といった形で利用されています。
家族信託が近年注目されている理由
家族信託が注目される主な理由には、従来の制度ではカバーしきれなかった課題を解決できる点にあります。ポイントは以下の3つです。
①認知症などによる資産凍結を防ぐ
認知症などで資産を有する方の判断能力が低下すると、本人の意思能力がないと判断され、銀行口座の引き出しや不動産の売却などができなくなります。家族信託であらかじめ受託者に権限を託しておくことで、こうした資産凍結を防ぎ、本人の生活に必要な資金を確保できます。
②成年後見制度より柔軟な財産管理が可能
・法定後見制度との違い
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になってしまった人の財産を守るための制度です。家庭裁判所の厳しい監督のもと、「財産の保全」が主な目的となるため、以下のような積極的な資産運用は原則としてできません。
- 不動産の売却や建て替え
- 株式や投資信託など、元本割れのリスクがある投資
- 相続税対策のための生前贈与
一方、家族信託は、本人が元気なうちに契約を結ぶことで、「積極的な財産の活用」が可能です。アパートの老朽化に備えた建て替えや、空き家となった不動産の売却なども、あらかじめ契約に定めておけばスムーズに行うことができます。
・任意後見制度との違い
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来の財産管理を任せる相手(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。家族信託と同様に、本人の意思を反映した自由度の高い契約が可能です。しかし、両者には財産管理の開始時期に大きな違いがあります。任意後見制度契約を結んでも、実際に財産管理が始まるのは本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点です。一方の家族信託は契約を結ぶことで、すぐに財産管理を始めることができます。判断能力の低下を待つ必要がないため、本人が元気なうちに運用を開始できるため、利益や資産の運用を任意後見制度より柔軟に行える可能性が高いでしょう。
このように、家族信託は財産管理の開始時期や運用の柔軟性において、他の制度にはないメリットを持っていると言えるでしょう。
③数世代にわたる資産承継を設計できる
家族信託は遺言書とも異なる相続対策ができます。遺言書では一次相続(自分が亡くなった後の相続)しか指定できませんが、家族信託では「自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら孫に」といったように、二次相続以降の承継先まで指定できます。受託者が有意義に財産の承継先を決められる点も注目される理由の1つです。
家族信託で相続が発生した際の注意点とは
家族信託を実際に運用している最中に、もしも契約に関係する方が亡くなった場合には、どのような影響があるでしょうか。この章では家族信託契約前に、あらかじめ知っておきたい相続時の注意点を解説します。
委託者が亡くなったケース
家族信託における「委託者」とは財産の所有者です。委託者が亡くなった場合、委託者の地位は相続対象となりますが、契約内容によっては契約が終了します。(例・委託者死亡で権利は消滅する、などの内容)
信託契約で「委託者が死亡しても信託を継続する」旨を定めていれば、信託は終了せず継続します。
受託者が亡くなったケース
「受託者」は委託者から託された財産を管理・運用する役割を担います。この役割を担う方が委託者より先に亡くなった場合、強制的に終了するのではなく委託者が新しく1年以内に選任されない場合に契約が終了します。受託者が死亡しても、信託財産は相続対象ではありません。
信託契約を継続させるためには、受託者の役割は不可欠であるためです。受託者不在を防ぐために、家族信託の契約を作る際には、「第二受託者」をあらかじめ指定しておくことも可能です。
例として、父親が委託者で長男が受託者の場合、あらかじめ第二受託者として次男を定めておけば、先に長男が亡くなってしまった場合でも速やかに次男が受託者となります。
また、委託者と受益者が協議し、第二受託者を決めることも可能です。信託法第62条4項により、協議でまとまらないなどのケースでは家庭裁判所で決めてもらう方法もあります。
|
信託法第62条4項 第1項の場合において、同項の合意に係る協議の状況その他の事情に照らして必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、新受託者を選任することができる。 |
受益者が亡くなったケース
「受益者」は、信託財産から得られる利益を受け取る権利を持つ人です。受益者が亡くなった場合、原則として受益者の相続人が受益権を相続するため、受益者固有の相続財産とあわせて遺産分割の対象になります。
ただし、あらかじめ信託契約事項で「受益者の死亡後の受益権の承継者」に、その権利が引き継げるように定めておくことも可能です。第2受益者など、次の受益者であると定められた方へ受益権を引き継ぎます。
家族信託では原則として受益者が亡くなっても信託契約は継続します。しかし、あらかじめ信託契約事項で受益者死亡時に契約を終了する旨を定めておくと、契約を終了させることも可能です。
家族信託で相続税が発生するケースを整理
家族信託は財産管理や円滑な事業承継に役立つ一方で、相続税の節税効果は期待できません。では、なぜ家族信託では相続税の対策にはならないのでしょうか。ここでは、家族信託と相続税の関係について整理します。
相続税の事例|課税対象となる人
家族信託で相続税が発生するのは「受益者」が亡くなった時です。相続税の課税対象者は信託契約の内容によって異なります。
①受益者が亡くなった後も、第2受益者が契約で設定されているケース
このケースでは、受益者死亡により第2受益者が受益権を相続するため、相続税の課税対象者は第2受益者です。
②受益者が亡くなり、信託契約も終了するケース
このケースでは残っっている財産を受け取ることになった相続人に相続税が課税されます。
家族信託が相続税の節税にならない理由
家族信託において、委託者は受益者を兼ねるケースがほとんどです。受託者が管理・運用を行ったとしても、信託財産は受益者がそのまま所有していることになります。
そのため、委託者が亡くなると受益者も亡くなることとなり、死亡後は受益権は相続財産と同様に扱われるため、相続税計算に入れることになります。遺留分についても対象となるため注意が必要です。家族信託を十分に理解していないと、思わぬ形で争族問題に発展するおそれがあるため、契約前は十分に弁護士や税理士などの専門家にアドバイスを受けた上で始めることが望ましいでしょう。
家族信託のメリットは成年後見制度よりも資産運用が柔軟である点であり、相続税の節税とは別のメリットがあると理解しておくことが大切です。
特例や控除はどうなる?
家族信託で信託された財産も、法定相続人が相続する場合は、相続税の計算において要件を満たしている場合は「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」等の特例・控除を利用することが可能です。
ただし、空き家特例については家族信託が含まれておらず、利用することができません。(※1)この点は租税特別措置法の通達によっても補足されているためご注意ください。
相続税の計算時に受けられる特例や控除を適用するためには、信託契約書の内容や受益者の条件など、適用要件を詳細に確認する必要があります。契約前に専門家による適切な助言が必要です。
(※1)空き家特例とは
「空き家特例」とは「被相続人の居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除の特例」と呼ばれる制度です。相続によって取得した空き家(被相続人、つまり亡くなった方が住んでいた家屋)を売却した際に、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円までを控除できる特例です。
家族信託が持つメリット
家族信託は、財産管理や円滑な承継に役立つ一方で、相続税の節税効果は期待できません。しかし、家族信託は柔軟に契約内容を設計できるなどのメリットがあります。この章では、家族信託が持つ主なメリットを解説します。
委託者の判断能力に左右されずに資産運用できる
家族信託の最大のメリットとして、委託者の判断能力が低下した場合でも、受託者が信託財産の管理・運用を継続できる点が挙げられます。委託者が認知症などで判断能力を失った場合、預貯金の引き出しや不動産の売買が困難になってしまいます。
このようなケースでは成年後見制度が利用されてきましたが、あらかじめ家族信託を組んでいれば、受託者が委託者の意思に基づいて財産を管理できるため、資産凍結のリスクを回避でき柔軟に資産運用を継続できます。相続税への直接的な節税効果はなくても資産運用により財産を増やすことが可能です。
成年後見制度よりも柔軟
成年後見制度は、本人の財産保護が目的であるため、財産の積極的な運用や相続税対策といった行為は原則として認められません。加えて、成年後見制度は以下に挙げるデメリットもあります。
■成年後見制度のデメリット
・家庭裁判所への申立て時などに費用がかかる
・一度決められると後見人の変更が難しい
・後見人への報酬が発生し、資産が減っていく
・家族と後見人の間で対立が起きることがある
・家庭裁判所へ定期的に報告を行う必要がある
・権限外行為を求める際も家庭裁判所の許可がいる
・成年後見制度は被後見人が亡くなるまでやめることができない(※2)
家族信託では、信託契約によってあらかじめ定めた目的(例・マンション経営や不動産の売却など)のために、受託者が柔軟に財産を活用できます。
(※2)
成年後見制度は高齢化の進行により利用者が増えることが予想されており、制度の見直しが検討されています。必要がなくなったら終了する、定期的な報告制度の見直しなども議論されており、今後法改正が行われる可能性があります。
遺産分割時のトラブルを減らせる
家族信託では信託契約書に、委託者の死後における財産の帰属先(第二受益者や帰属権利者)をあらかじめ定めておくことが可能です。これにより、遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続人同士の無用なトラブルを防ぐことができます。
特に収益が多い不動産オーナーや、安定した事業承継を検討されている方などは、節税だけではなくスムーズな相続を目指して家族信託を契約しておくこともおすすめです。
倒産隔離機能がある
家族信託を設定することで、信託財産は委託者や受託者自身の財産とは法的に区別されます。そのため、もし委託者が破産した場合でも、原則信託財産が差し押さえられることはありません。これは信託法で定められた「倒産隔離機能」によるもので、信託財産を保全する上でメリットとなります。
ただし、受益者が破産した場合は受益権が破産財団に組み入れられるため、委託者が受益者を兼ねる場合は、破産の影響は受けることになります。倒産隔離機能を有効にしておきたい場合は受益者を委託者以外にする必要がありますが、贈与の問題が発生するため慎重に税理士に相談することがおすすめです。
債権者への弁済を逃れることを目的に家族信託契約を結んでいた場合は、債権者に詐害信託であると指摘を受け、契約が取り消されるおそれもあります。
遺言書との併用も可能
家族信託と遺言書は併用可能です。
家族信託では、信託財産の帰属先しか定めることができません。しかし、信託していない財産については遺言書を作成しておくことで、残りの財産の承継先を明確に指定できます。これにより、すべての財産を円滑に次の世代に引き継ぐことが可能です。
特に相続人同士が財産を巡って対立するおそれがある場合は、家族信託と遺言書を併用しておくことでトラブルを防ぐ効果が高くなります。
家族信託と遺言書は、それぞれ異なる役割を持つため併用には法的知識も必要です。また、信託登記などを必要とするケースもあるため、司法書士の知識が必要な場合もあります。
専門家のサポートを受けながら契約書などを作り、税務と紛争のいずれにも備えた対策を行うことがおすすめです。
まとめ
本記事では話題の家族信託について、相続時の注意点を中心に制度のしくみも交えながら詳しく解説しました。家族信託はまだ認知度が低い制度ですが、高齢社会の進行や成年後見制度のデメリットなどを背景に、近年注目が高まっています。財産を安全に家族へ移転させていくために、贈与制度をも比較しながら検討されることもおすすめです。
しかし、相続税の課税など専門知識も必要となるため、専門家に相談しながら慎重に検討しましょう。