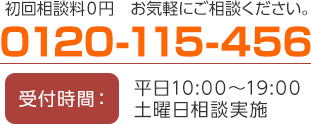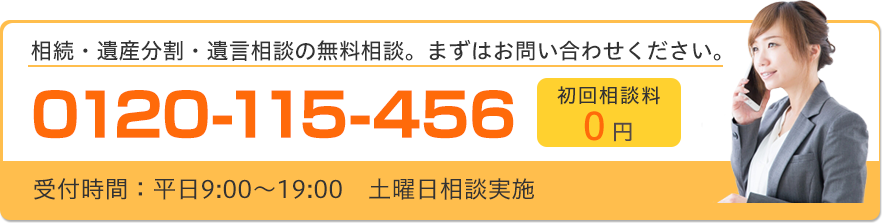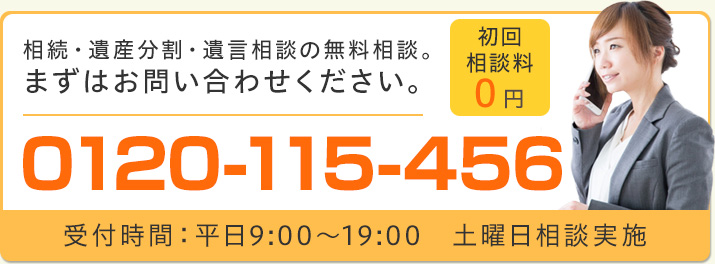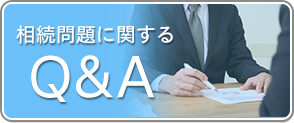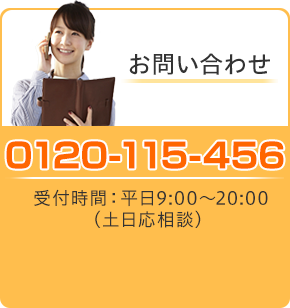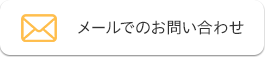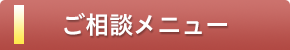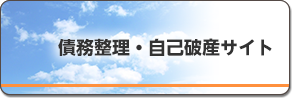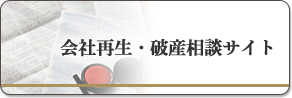相続登記における登記書類の保管期間一覧
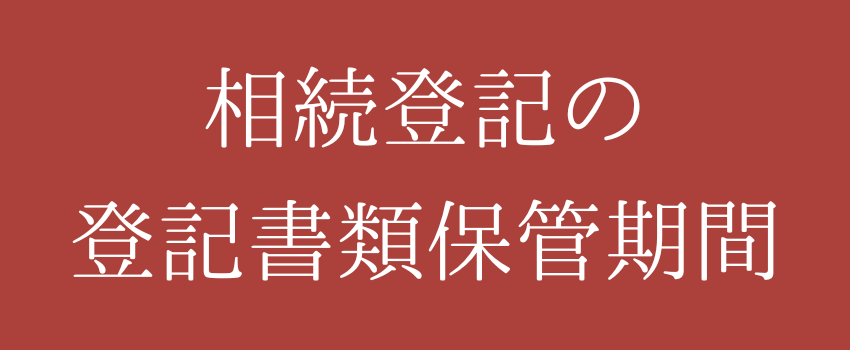
相続のご相談をお受けしていると、「これまでに登記した書類をもう一度確認したいのですが可能ですか?」とご質問をいただくことがあります。
土地や建物の登記記録(いわゆる登記簿)や登記の申請書の保存期間は、不動産登記法(以下では「法」と表記します)によって定められています。
書類によって保存期間が異なりますので、確認したいと思った時点で、「まだ保存されているもの」と「すでに破棄されてしまったもの」がある可能性があります。
下記は、代表的な登記簿や登記申請書の保存期間をまとめたものです(参照:法務局資料)。
ご参考にしてみてください。
永久保存
①登記記録(登記簿)
②地図(法第14条第1項)
③地図に準ずる図面(法第14条第4項)
④土地所在図及び地積測量図
⑤建物図面及び各階平面図
⑥その他信託目録、共同担保目録、工場財団目録、地役権図面など
50年間保存
閉鎖した土地の登記記録(登記用紙)
30年間保存
①閉鎖した建物の登記記録(登記用紙)
②表示に関する登記の申請情報とその添付情報
③権利に関する登記の申請情報とその添付情報
④滅失した建物の建物図面及び各階平面図
⑤閉鎖された地役権図面
20年間保存
①抹消された信託登記の目録
②閉鎖された工場財団登記の工場財団目録
10年間保存
共同担保目録に記録されているすべての事項が抹消された共同担保目録
相続に関するご相談は弊所まで
弊所では相続に関するご相談をお受けしております。
相続は、相続人同士の感情の摩擦から紛争化したり、登記などの手続きが複雑だったりと、知識の無い方がご自身で行われるのは難しいことが多いです。
弁護士にご相談頂ければ、法的な知識や経験を駆使して適切な手続きの実行や、紛争の対応をいたします。
初回相談料は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。