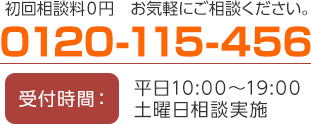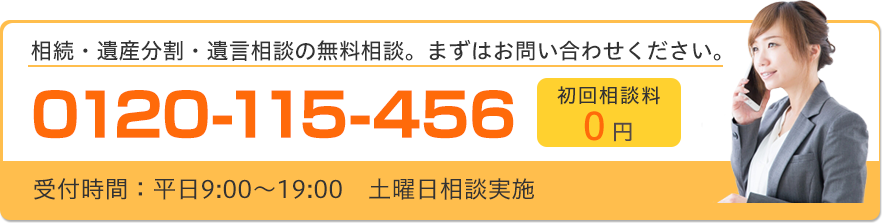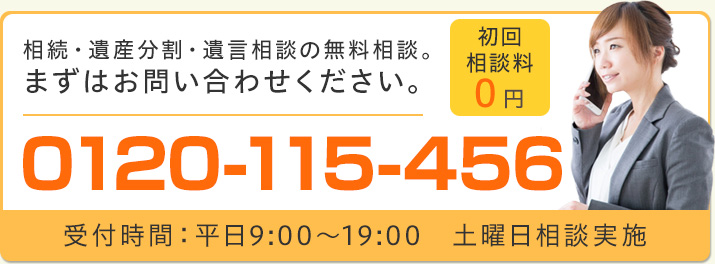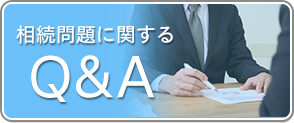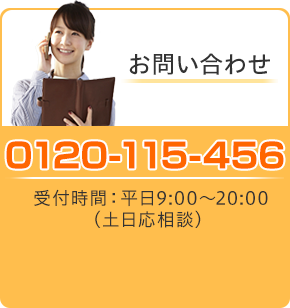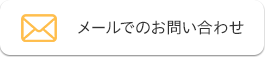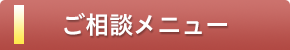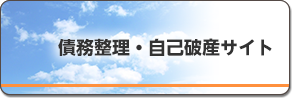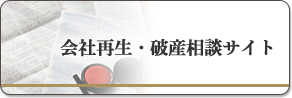相続放棄しても空き家を管理する義務は消えない?責任回避の条件と手続き、注意点を解説
「親や親族が亡くなり、思いがけず不動産を相続することに……管理するのが面倒なので相続放棄を検討しているが、それが正解なのかわからない」
そんな問題に直面している方はいませんか?
「相続放棄をしても、不動産の管理義務は残る」としたらどうでしょう。きっと不安になるはずです。
本記事では、相続放棄後に残ってしまう管理義務の実態と、義務から解放されるための具体的な方法を、相続問題に詳しい弁護士が分かりやすく解説します。(監修:弁護士法人i)
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が相続する権利を法的に放棄するための手続きです。相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)のすべてを相続する地位を完全に失います。
相続放棄をしたのになぜ「管理義務」が残るのか?
相続放棄をすると相続人としての地位を失うのですから、相続財産である土地や建物の管理義務も当然なくなると考えるのが自然です。
しかし、法律はそうなっていません。相続放棄をしても、一定の条件下では相続財産の管理義務が残ると定められています(民法940条)。
相続放棄したのに管理義務が発生する理由
なぜ相続放棄をした相続人に管理義務が課せられるのでしょうか。
それは、空き家や土地が管理されずに放置されると、建物の倒壊、不法投棄、放火、雑草の繁茂による近隣トラブルなど、周辺地域に重大な悪影響を及ぼす危険があるからです。
こうした「誰も責任を負わない危険な不動産」の発生を防ぎ、社会全体の安全を守るために、法律は次の管理者が見つかるまでの一時的な措置として、相続放棄者に最低限の管理を義務付けているのです。
民法940条は2023年改正でどう変わった?
相続放棄後にも発生する管理義務は、民法第940条に定められています。2023年4月施行の改正民法により、ルールがより明確になりました。
(民法940条・改正前後の違い)

〈改正のポイント〉
改正法のポイントは2つあります。
- 管理義務を負う者の限定
改正前は、「相続放棄をしても、次に相続人になる者が管理を始めることができるまでは継続して管理義務を負う」とされており、誰が管理義務を負うのかがやや曖昧でした。改正後は「相続放棄をした者かつ放棄時に相続財産を現に占有している者」にだけ管理義務があると限定されました。
例えば、親が所有する家に同居していた一人息子が、親の死亡時にすぐ相続放棄したとしましょう。この場合、「放棄の時に相続財産を現に占有している」ことになりますから、息子は家の管理義務を負います。しかし、一人息子が親と別居していた場合は、「現に占有している」とは言えませんから管理義務は負いません。
- 管理義務の終了時期の明記
改正前は、管理義務が終わるタイミングを「放棄によって相続人となった者が管理を始めることができるまで」と定めていました。そのため、親と別居している一人息子が相続放棄したとしても、相続放棄によって相続人となったおじ・おば(死亡した親の兄弟)が家を管理できる準備が整うまでは息子が管理義務を負い続けるという理不尽な結果になっていたのです。
改正後は、「相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで」と明記されたため、管理義務の終了時期が明確になり、管理にともなう負担感が大幅に軽減しました。
以上のとおり、2023年改正により相続放棄者の責任の範囲が限定される一方で、「現に占有している」場合には、財産を他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで管理義務を負うことが確定しました。
この改正内容を知らなかったために、相続財産を占有した状態でうっかり相続放棄してしまうと、予期せぬ管理義務を負うことになるので注意しましょう。
相続放棄は、単に義務を免れるための制度ではありません。自分が相続放棄をしても問題ないか不安がある場合は、弁護士など相続の専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄後の管理義務〜範囲・期間のポイント
相続放棄後に生じる相続財産の管理義務とは、具体的に「何を」「いつまで」管理しなければならないのでしょうか。3つのポイントに分けて紹介します。
管理義務は「保存行為」に限られる
相続放棄後に相続人が負う管理義務の範囲は、相続財産の価値を維持するための「保存行為」に限られます。保存行為とは「放置すると第三者に迷惑がかかる事態を防ぐための最低限の行為」と考えるとよいでしょう。
- 建物の場合:雨漏りの修繕、窓ガラスが割れている場合の補修、施錠の確認、台風前の補強など。
- 土地の場合:雑草が隣地にはみ出さない程度の草刈り、ゴミの不法投棄の監視・簡易な撤去、危険なブロック塀の応急処置など。
建物の大規模なリフォームや解体、土地の売却などは保存を超えた「処分行為」ですので行ってはいけません。処分行為を行うと、後述する法定単純承認とみなされ、相続放棄が無効になる可能性があります。
管理義務が終了するのは、他の相続人または清算人に引き渡したとき
相続放棄時に土地や建物を現に占有していたために、相続放棄者が管理義務を負うことになった場合、特に気になるのが「管理義務はいつまで続くのか?」ということでしょう。
管理義務が終了するタイミングは、以下の2つです。
- 他の相続人が管理を始めた時
自分以外の相続順位の相続人(例えば、子が全員放棄した場合の親の兄弟姉妹など)に対して、自分が管理していた相続財産を引き渡した時点で管理義務は終了します。ただし、相続人が自分しかいない場合、次にあげる「相続財産管理人の選任、財産の引き渡し」が行われるまで管理義務が継続するので注意してください。
- 相続財産清算人が選任され、財産を引き渡した時
「相続財産清算人」が家庭裁判所によって選任され、清算人に不動産を含む相続財産一式を引き継いだ時点で、管理義務は完全に終了します。相続財産清算人については後ほど詳しく説明します。
相続財産の管理義務を怠ると損害賠償責任のリスクあり
相続財産の管理義務を果たさず相続財産を放置していると、最悪の場合、第三者に対する損害賠償責任や行政からの指導勧告といったリスクが生じます。
事例1:倒壊事故による損害賠償
管理を怠っていた空き家のブロック塀が地震で倒壊し、隣家の壁や車を破損させてしまった。修理費用として数百万円の損害賠償を請求された。
事例2:延焼による損害賠償
放置された空き家に不審者が侵入して放火され、複数の隣家にも延焼。近隣住民から数千万円の損害賠償を求められた。
事例3:行政からの勧告
空き家を放置した結果、紛れ込んだ野生動物の死骸が原因で害虫が大量発生。近隣からの苦情が殺到し、自治体から「特定空家」に指定されてしまう。行政からの改善指導・勧告を無視していたところ、最終的に行政代執行で家を解体され、高額な費用を請求された。
以上の事例のように、相続財産の管理義務を怠ると、管理不備が原因で生じたトラブルにより多額の損害賠償等を請求される可能性があります。
自分の将来に“思わぬ負債”が降りかかる前に、下記チェックリストで自己点検してみましょう。
チェックリスト:あなたは大丈夫?相続放棄後の管理義務セルフチェック
- 相続放棄した不動産の現在の状況(老朽化の程度、雑草など)を把握していますか?
- 最後に現地を確認したのはいつですか?定期的な見回りを行っていますか?
- 施錠や戸締まりは確実になされていますか?
- 近隣住民や自治体から、管理に関する連絡や指導を受けていませんか?
- 連絡や指導を受けている場合、それを放置していませんか?
一つでも該当する項目があるなら、すぐに対策を取る必要があります。
相続財産清算人に財産を引き渡せば管理義務から解放される
相続放棄後に相続財産の管理義務を負うことになった者が、その管理義務から解放されるにはどうすればよいのでしょうか。最も確実な方法は、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申立て、選任された相続財産清算人に財産を引き渡すことです。
相続財産清算人とは?
相続財産清算人(以下、清算人)とは、家庭裁判所によって選任される専門家(主に弁護士)で、被相続人の財産を総合的に管理・調査し、最終的に清算する役割を担います。
清算人は、相続人がいない財産や相続放棄された財産の管理・処分を行います。具体的には、債権者への弁済や特別縁故者への財産分与などです。
必要な処分を行った後、さらに相続財産が残る場合、相続財産は国庫に帰属します。
清算人の選任を請求できる利害関係人は?
家庭裁判所が清算人を選任するには、利害関係人または検察官からの請求が必要です(民法952条)。
〈代表的な利害関係人〉
- 被相続人の債権者
- 受遺者(遺言により遺贈を受ける者と定められた者)
- 特別縁故者(被相続人の事実上の養子、内縁の配偶者、被相続人の療養看護を尽くした者など)
本来、相続放棄をした相続人は利害関係人ではありません。相続放棄をすると、相続開始時にさかのぼって相続人の地位を失うからです。
しかし、放棄後に管理義務を負うことになった相続人は、例外として利害関係人に含まれるので、清算人の選任を請求できます。
選任された清算人に対して相続財産を引き渡すと、あらゆる管理権限が清算人に移ります。清算人に財産を引き渡した時点で、相続放棄後の管理義務から完全に解放されるのです。
管理に関連する「コスト」にも注意
相続財産の管理にはお金がかかります。相続放棄後の管理義務問題も、その多くが「コストの問題」と言えるでしょう。以下の2つは、コストの問題が特に大きいケースです。
山林のように管理コストが大きい不動産を相続する場合
大規模な山林は、いざ管理するとなると大変なコストを要します。処分しようにもなかなか買い手がつかないことが少なくありません。
このような相続財産を俗に「負動産」と言います。
相続財産の中に「負動産」がある場合、「相続放棄をすべきか」「管理費用はどのくらいかかるか」などを、相続人だけで適切に判断するのは相当困難です。どのような相続の仕方が最善であるか、弁護士のような相続のプロに相談すると良いでしょう。
清算人の選任費用を捻出できない場合
清算人選任には相応の費用(清算人の報酬や事務費など)がかかります。相続財産の中の預貯金等に余裕がある場合は、清算人のための費用も問題なく払えるでしょう。
しかし、相続財産の中に目ぼしい資産がない場合は、清算人の費用を確保するための「予納金」を家庭裁判所に納めなければなりません。不動産や株式など、現金・預貯金よりも処分の手間がかかる資産が多いケースでは、清算人の作業レベルも上がるため、100万円前後の予納金を要することもあります。
自分で管理する場合のコストと予納金の金額を比較して、どちらが効率的かを慎重に考える必要があります。相続人だけで判断することが難しいのであれば、相続財産の管理実務に詳しい専門家(不動産鑑定士や弁護士など)にアドバイスを求めると良いでしょう。
管理義務がなくても固定資産税から逃れることはできない
不動産を管理している間、自治体から固定資産税納税通知書が届くことがあります。
固定資産税の課税基準日は1月1日です。課税基準日の到来前にすべての相続人が相続放棄をすれば、納税義務者は被相続人のままですから、相続人あての固定資産税の納税通知書が届くことはありません。
しかし、相続放棄をする前に1月1日が到来すると、相続人が固定資産税の納税義務者になるため、4〜6月頃に相続人を納税義務者とする納税通知書が届くことになります。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議によって不動産を相続した者に固定資産税を負担させることもできるでしょう。しかし、相続人が子供一人しかいない状態で、相続放棄をする前に1月1日が到来してしまうと、その子供が納税義務者に確定します。
相続財産の管理義務と納税義務は別物です。相続財産清算人を選任し、管理義務から解放されたとしても、納税義務を免れることはできませんので注意しましょう。
安心して相続放棄するために|専門家相談のポイント
相続放棄とそれに伴う管理義務の問題は、法律の専門知識が不可欠です。不安や疑問を感じたら、なるべく早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談すべき「タイミング」
以下のような状況に当てはまったら、迷わず弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
- 相続放棄すべきか承認すべきか、リスクを考慮した判断が難しい
- 管理義務の具体的な範囲や対処法が分からずとても不安
- 相続財産清算人の選任を検討している
- 不動産の管理について近隣や自治体からクレームを受けている
- NG行為(法定単純承認)をしてしまったかもしれない
問題が小さいうちに相談するほど、選べる選択肢は多くなり、解決までの時間と費用は少なくて済みます。将来の大きな損害や後悔を防ぐためには、早めの相談が最善の策です。
相談する前に準備したい「情報・質問」
専門家に相談する際は、事前に以下の情報を整理しておくと、スムーズで的確なアドバイスが受けられます。
- 誰がいつ亡くなったか(被相続人・死亡日)
- 自分と被相続人との関係
- 分かっている範囲での財産(プラス・マイナス)の一覧
- 管理義務の対象となっている不動産の所在地や状況
- 他の相続人の状況(連絡先、相続放棄の意向など)
- 一番聞きたいこと、不安に思っていること(質問リストを作成)
これらの情報をメモにまとめ、戸籍謄本や不動産の資料など、手元にある関係書類を持参して相談に臨みましょう。
無料相談をご活用ください
弁護士への相談は費用がかかると思われがちですが、多くの法律事務所では初回相談を無料としています。まずは無料相談を活用して、問題の全体像と解決への道筋、そして依頼した場合の費用について説明を受けるとよいでしょう。
複数の事務所で相談し、説明の分かりやすさや相性、費用などを比較検討することも有効です。法テラスなどの公的サービスも選択肢に入れ、自分にとって最適な専門家のサポートを受けてください。
安心して相続放棄したい方、管理義務の問題にお悩みの方は「弁護士法人 i」へ
相続放棄をしてもあらゆる責任から解放されるわけではありません。「相続放棄後の管理義務」という落とし穴を知っているのは、よほど相続問題に関心がある人だけでしょう。
関西地方で相続管理問題にお悩みの方は「弁護士法人 i」へお気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です。相続・遺産問題の豊富な知見を生かして、「お客様にとって、どのような選択肢があり、いかなる方法がベストなのか」をご提案いたします。